子育てをしていると、色々な病気や体調不良に直面しますよね。その中でも、突然激しく吐き続ける「自家中毒」は、パパやママを不安にさせる病気の一つです。
「この吐き気はいつまで続くんだろう…」 「どうしてこんなに苦しそうなんだろう…」
今回は、そんな不安を少しでも和らげるために、子どもの自家中毒(周期性嘔吐症)について、原因や症状、そして家庭でできる対処法まで、分かりやすく解説していきます。
自家中毒(周期性嘔吐症)ってどんな病気?
自家中毒は、元気だった子どもが突然、何度も激しく吐いてしまう病気です。数時間から数日吐き続け、その後自然に治まるのが特徴です。
正式には「周期性嘔吐症」、あるいは「アセトン血性嘔吐症」とも呼ばれます。
この病気の正体は、体内で作られる「ケトン体」という物質です。本来、私たちの体は、ブドウ糖をエネルギー源として使いますが、ブドウ糖が足りなくなると、代わりに脂肪を分解してエネルギーを作ります。その際に発生するのがケトン体です。
特に2歳から10歳くらいの子どもは、エネルギー代謝の仕組みが未熟なため、疲労やストレス、空腹などでブドウ糖が不足すると、ケトン体が過剰に作られてしまい、それが中毒症状を引き起こして吐き気をもよおしてしまうのです。
子どもの自家中毒、こんな症状に注意!
自家中毒の主な症状は、なんといっても「嘔吐を繰り返すこと」です。
嘔吐物から甘酸っぱい匂いがすることがあり、これはケトン体が原因で血液が酸性に傾くことで起こります。
症状が重くなると、以下のような症状も現れることがあります。
- 胆汁や血液が混ざった茶色の嘔吐
- ぐったりしていて元気がない
- 手足のしびれ
- 腹痛や頭痛
- 軽い意識障害
「いつもと違うな」と感じたら、すぐに病院を受診しましょう。
自家中毒はなぜ起こる?主な原因と対処法
自家中毒の主な原因は、肉体的な疲労と精神的なストレスです。
具体的には、
- 風邪や発熱などの感染症
- 運動会や旅行などのイベント
- 習い事や新しい環境でのストレス
- 食事をとらない時間が長くなる
といったことが引き金になることが多いです。
また、嘔吐を繰り返すことで脱水症状や低血糖になりやすいので、家庭でのケアが非常に重要になります。
病院に行くべきタイミングと検査・治療法
自家中毒が疑われる場合は、自己判断せず、必ず病院を受診しましょう。特に、嘔吐が続いて水分補給ができない場合は、脱水症状を防ぐために早めの受診が必要です。
病院では、尿検査や血液検査でケトン体の量を調べ、診断されます。
残念ながら、自家中毒には特効薬がありません。治療は、嘔吐による脱水や低血糖を防ぐための対症療法が中心です。
多くの場合、点滴で水分や糖分を補給して、症状が落ち着くのを待ちます。
「点滴なんてかわいそう…」と思うかもしれませんが、子どもの体を守るために必要な処置なので、ここは病院の先生にお任せしましょう。
自家中毒の予防と家庭でのホームケア
自家中毒は、再発しやすい病気でもあります。子どものつらい症状を繰り返さないために、家庭での予防とケアをしっかり行いましょう。
1. 生活リズムを整える
規則正しい生活は、子どもの体を疲れから守る一番の予防策です。
- 十分な睡眠時間を確保する
- 早寝早起きを心がける
- 休日はしっかり体を休ませる
また、食事も大切です。空腹時間が長くなるとケトン体が増えやすくなるので、朝食・夕食をしっかり食べさせることを心がけましょう。
もし食欲がない場合は、うどんやおかゆなど消化の良い炭水化物を少量でも食べさせてあげると良いですよ。
2. ストレスを溜めさせない
子どもも大人と同じように、ストレスを感じています。
- 環境の変化(進級・進学、習い事など)
- きょうだいとの関係
- 親の仕事や家庭の状況
など、様々なことがストレスの原因になります。
「最近元気がないな」「いつもと様子が違うな」と感じたら、子どもとじっくり向き合う時間を作ってあげてください。一緒に散歩に行ったり、好きな遊びをしたりして、気分転換をさせてあげましょう。
3. こまめな水分・糖分補給
嘔吐が落ち着いてきたら、脱水を防ぐために少しずつ水分を補給しましょう。
おすすめなのは、糖分も含まれている経口補水液やスポーツドリンクです。
まとめ
自家中毒は、突然発症してパパやママを心配させる病気ですが、成長とともに自然と治っていくことがほとんどです。
この記事が、お子さんが自家中毒になった時の不安を少しでも和らげるお役に立てれば嬉しいです。
万が一の時に備えて、かかりつけの小児科を決めておくこと、そして子どものSOSサインを見逃さないように、日頃からしっかり見守ってあげてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

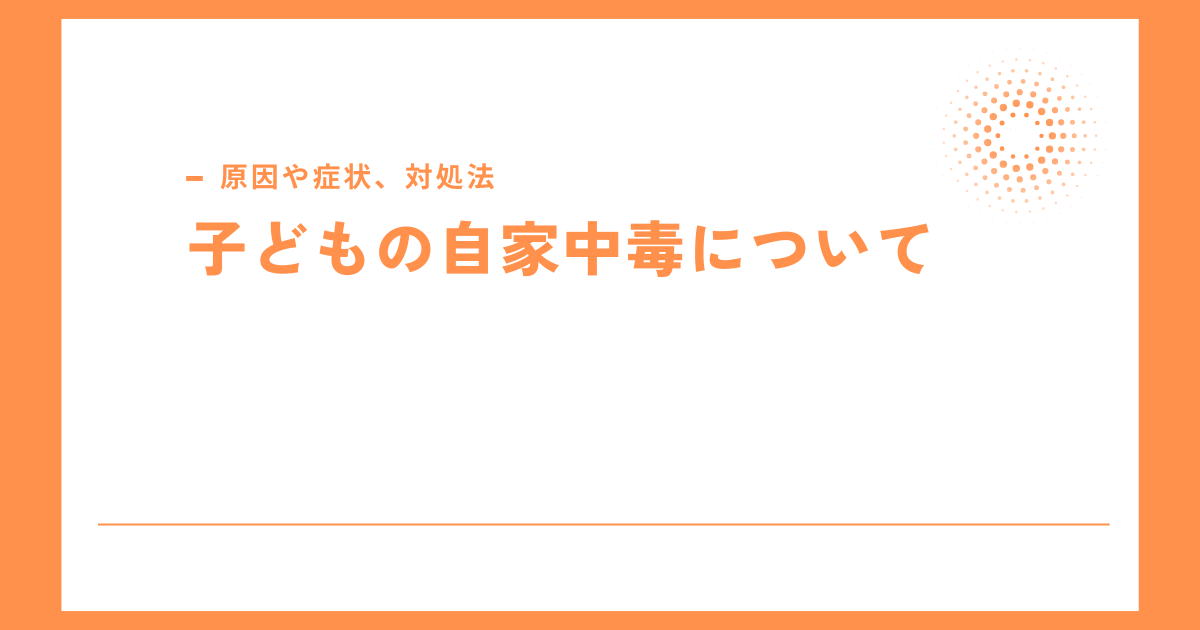
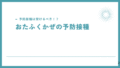
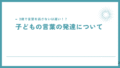
コメント