節句は皆さん聞いたことある方も多いかと思いますが、実際に初節句は何をするのか分からない方もいらっしゃるのではないかと思います。
そこで今回は、女の子と男の子の初節句について、お祝いする理由や方法などを紹介したいと思います。
初節句とは?
節句とは、中国の風習が由来になっている季節の変わり目に行う年中行事です。
日本では、五節句(七草粥を食べる「七草の節句」、ひな祭りとも言う「桃の節句」、こどもの日にあたる「端午の節句」、笹の葉に願い事を記した短冊を飾る「七夕の節句」、栗ご飯を食べる「菊の節句」)がお祝いの行事として定着しました。
いつやるの?
女の子と男の子で異なります。女の子は桃の節句の日(3月3日)、男の子は端午の節句の日(5月5日)に、健やかな成長を祈ってお祝いします。
2月生まれの女の子や4月生まれの男の子は、生後間もない時期に初節句を迎えることになるので、翌年に初節句のお祝いをすることもあります。
お祝いする理由
初節句をお祝いする理由は、女の子(桃の節句)と男の子(端午の節句)で異なります。
桃の節句をお祝いする理由
桃の節句と呼ぶのは、旧暦の3月3日が桃の花が咲く頃だからとされています。
平安時代の貴族は「上巳(じょうし)の節句」と呼ばれる3月はじめの巳の日に、自分に降りかかる災いを紙人形に託して川に流す「流し雛」を行っていました。
室町時代に、この行事が巳の日から3月3日に定まり、紙から雛人形へと変わって今のような女の子の厄除けと成長を祈る行事になったと考えられています。
端午の節句をお祝いする理由
「端午」とは、もともと5月のはじめの午(うま)の日のことでしたが、「午」と「五」の音が同じことから5月5日が端午の日となりました。
その後、薬草である菖蒲(しょうぶ)は邪気を払うと考えられていたことと、「武を尊ぶ」という意味の「尚武(しょうぶ)」という言葉と読みが同じことから、鎌倉時代の武家では5月5日を祝うようになりました。
それが江戸時代以降、庶民に広がって男の子の成長を祝う日となったとされています。
お祝いする方法
女の子なら雛人形を、男の子なら五月人形や兜、鯉のぼりなどを飾り、お祝いをします。
また、初節句では、赤ちゃんの成長を祝うために特別な料理を食べることが一般的です。女の子の初節句であれば、ちらし寿司やハマグリのお吸い物、男の子の初節句であれば、ちまきや柏餅などが振る舞われます。
お祝いのマナー
初節句にはお祝いをするうえでのマナーや風習がいくつかあります。その一例を以下でご紹介します。
地域によっても異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
飾りは誰が用意するの?
地域にもよりますが、本来は初節句の飾りは母方の両親が贈る習わしでした。
近年では、飾りを誰が用意するのかあまりこだわらなくなってきており、パパとママが自分たちで用意することもあれば、鎧兜は母方、こいのぼりは父方のように双方で分けて贈るケースも多いようです。
飾りつけはいつからいつまで?
初節句の飾りを飾る日としまう日は厳密には決まっていませんが、以下のような目安があります。
女の子の初節句の場合、2月4日の立春から桃の節句の1週間前くらい(2月24日頃)までに飾るのが一般的です。
長く飾り続けるのは縁起が悪いとされているので、3月3日を過ぎたらなるべく早めにしまいましょう。
男の子の初節句の場合、鎧兜やこいのぼりは春のお彼岸(3月20日頃)が過ぎれば飾ってもよいとされていて、4月に入ってから飾る家庭が多いようです。
しまう日は女の子の初節句のように急ぐ風習はありませんが、5月中旬くらいまでを目安にしましょう。
初節句のお返しは?
初節句のお祝いには、基本的にお返しは必要ないとされています。
もしお返しをする際は、パパやママの両親など近い親戚の場合、お祝いの席に招待するのが一般的です。
友人や他の親戚にお返しをする際は、「内祝い」として、もらった金額の1/2~1/3程度の品物を贈るのがオススメです。
まとめ
初節句は一度きりになるので、初めて飾る雛人形や鎧兜はぜひ写真を撮って赤ちゃんとの思い出にするのもいいですね。
パパ、ママが楽しんで行うことが一番赤ちゃんにとっても楽しく過ごせることだと思うので、全力で楽しましょう。写真スタジオなどで写真を撮ってもいいかもしれませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

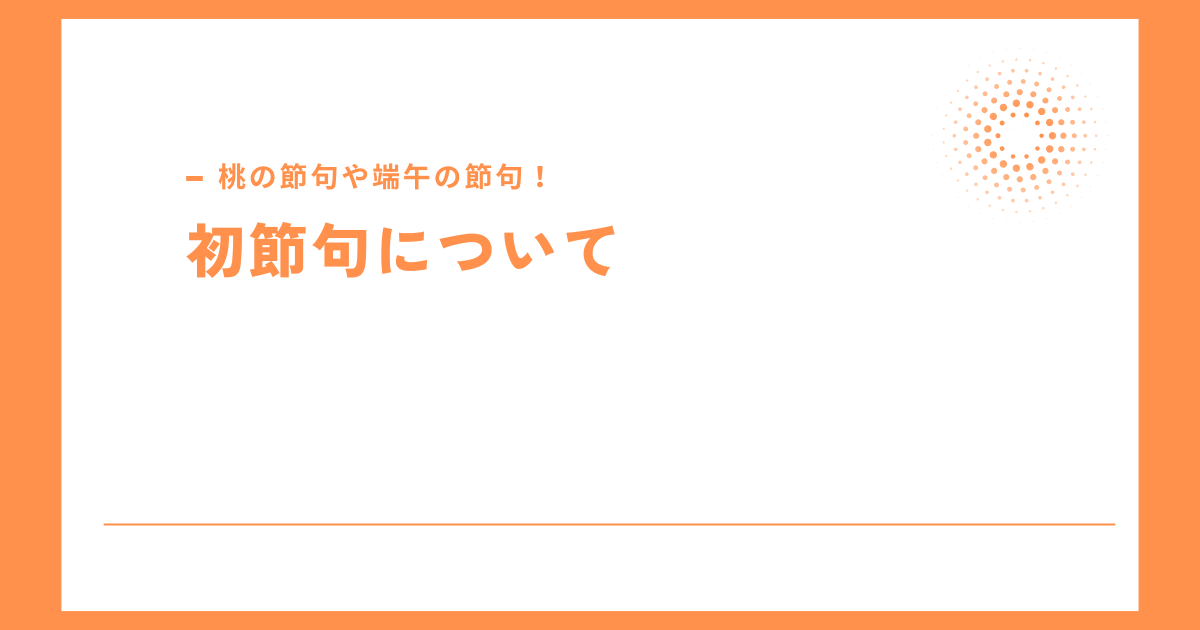
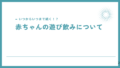

コメント