「うちの子、もしかして癇癪持ち?」
もしも、子どもが激しく泣き叫んだり、床にひっくり返ったりしている姿を目の当たりにしたら、不安になってしまいますよね。でも、安心してください。
1歳頃から始まる癇癪(かんしゃく)は、多くの子どもが通る成長の1つのステップです。
この記事では、
- 1歳児が癇癪を起こす原因
- 具体的な症状
- 成長に合わせた対応方法
- 病院に相談すべきかの判断基準
などを、わかりやすく解説します。
そもそも癇癪って何?1歳児にも起こるの?
「癇癪」と聞くと、少しネガティブなイメージを持つかもしれません。
でも、実は「自分の思い通りにいかないことに対する、激しい感情の爆発」のことです。
これは、赤ちゃんの成長過程で起こる自然な反応なんです。
一般的に、癇癪は1歳を過ぎた頃から現れ始め、2〜4歳頃にピークを迎えます。そして、5歳を過ぎると少しずつ落ち着いていく傾向にあります。
赤ちゃんや1歳児が癇癪を起こす3つの原因
なぜ1歳の子は、突然、激しく泣いたり怒ったりするのでしょうか?
主な原因は、以下の3つです。
- 「〜したい!」という欲求不満
- 言葉にできないもどかしさ
- 疲労や空腹などの不快感
1. 「〜したい!」という欲求不満
1歳を過ぎると、「自分でやりたい!」という自我が芽生え始めます。
スプーンでご飯を食べたい、おもちゃを自分で取って遊びたい、など、好奇心も旺盛になりますよね。
しかし、この時期は、まだ体が思い通りに動かせません。「〜したいのに、できない!」という、もどかしさが、癇癪として現れてしまうのです。
2. 言葉にできないもどかしさ
この時期の子どもは、言葉で自分の気持ちや要求を伝えるのがまだ難しいですよね。
「お腹が空いた」「眠たい」「もっと遊びたい」など、頭の中にはっきりとした思いがあるのに、それをうまく伝えられない。
この「言葉にできないもどかしさ」が、癇癪という形で爆発してしまうのです。
3. 疲労や空腹などの不快感
大人でも、疲れていたりお腹が空いていると、イライラしやすくなりますよね。
これは子どもも同じです。
特に1歳児は、自分の不調をうまく伝えられないため、「眠い」「お腹空いた」「暑い」といった不快感を、癇癪で表現することがあります。
1歳児の癇癪はどんな症状?
1歳児の癇癪の症状には、個人差がありますが、一般的には次のようなものが見られます。
- 大声で泣く、叫ぶ
- 手足をバタバタさせる
- 床にひっくり返ってジタバタする
- ものを投げる
- 噛みつく、引っかく
これらの行動は、「自分の気持ちをどうにか伝えたい!」という心の叫びです。
もし子どもがこのような行動をしても、「成長の証なんだな」と冷静に受け止めることが大切です。
癇癪が起きたときの4つの対処法
「癇癪が始まったら、どうすればいいの!?」と焦ってしまうママ・パパも多いはず。
ここでは、子どももママ・パパも落ち着ける、4つの対処法をご紹介します。
1. 気持ちを代弁してあげる
癇癪は、子どもからの「気持ちをわかってほしい!」というサインです。
もし子どもがうまく話せなくても、
「〜したかったんだね」 「〜が嫌だったんだね」
のように、パパ、ママが子どもの気持ちを言葉にしてあげましょう。
「自分のことをわかってくれている」と感じることで、子どもは安心し、落ち着きを取り戻しやすくなります。
2. 無視はしない
「もう勝手にして!」と、つい無視したくなる気持ちもわかります。
でも、癇癪のときに子どもを無視することは避けましょう。
無視されると、子どもは「自分の気持ちを表現しても無駄なんだ」と感じてしまい、自己肯定感が下がってしまう可能性があります。
子どもの激しい感情表現を「受け止めているよ」という姿勢を見せることが、何よりも大切です。
3. 抱きしめる
子どもが泣きわめいてどうしようもないときは、ぎゅっと抱きしめてあげましょう。
温かいぬくもりを感じることで、子どもの心は落ち着きを取り戻しやすくなります。
また、抱きしめることは、パパ、ママ自身の気持ちを落ち着かせる効果もあります。
4. 外では場所を移動する
電車やバス、レストランなど、公共の場で癇癪が始まったら、まずは周りの人から離れましょう。
人目がある場所だと、パパ、ママも焦ってしまいがちです。
一度落ち着ける場所に移動してから、子どもと向き合うことが大切です。
「電車の中では静かにする」といったマナーを教えるのは、もう少し大きくなってからでも大丈夫です。
癇癪がひどい…発達障害の可能性は?
「うちの子の癇癪、もしかして普通じゃない?」
このように不安を感じ、発達障害を心配されるパパ、ママもいるかもしれません。
癇癪は、発達障害のサインの一つと言われることもありますが、「癇癪=発達障害」ではありません。
ほとんどの場合、癇癪は成長の一環として起こります。
しかし、
- 癇癪が1日に何度も、激しく起こる
- 1回の癇癪が非常に長く続く
- 明らかな理由がないのに、毎日癇癪を起こす
- 他の子と比べて、明らかにコミュニケーションがとりにくい
といった状態が続く場合は、かかりつけの小児科医や地域の相談窓口に相談してみるのも1つの方法です。
専門家に話を聞いてもらうことで、パパ、ママ自身の気持ちが楽になることもありますよ。
まとめ
毎日続く癇癪に、疲れてしまうのは当然のことです。
「どうして私だけこんなに大変なの…」と、孤独を感じてしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、一人で抱え込まずに、周りの人に頼ってOKです。むしろ周りの人を頼りましょう。
- パートナーや家族に話を聞いてもらう
- 友人や先輩ママに相談する
- 地域の育児相談窓口を利用する
誰かに話すだけでも、気持ちは軽くなります。
「癇癪=成長の証」と前向きに捉えつつも、自分の心のケアも忘れないようにしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

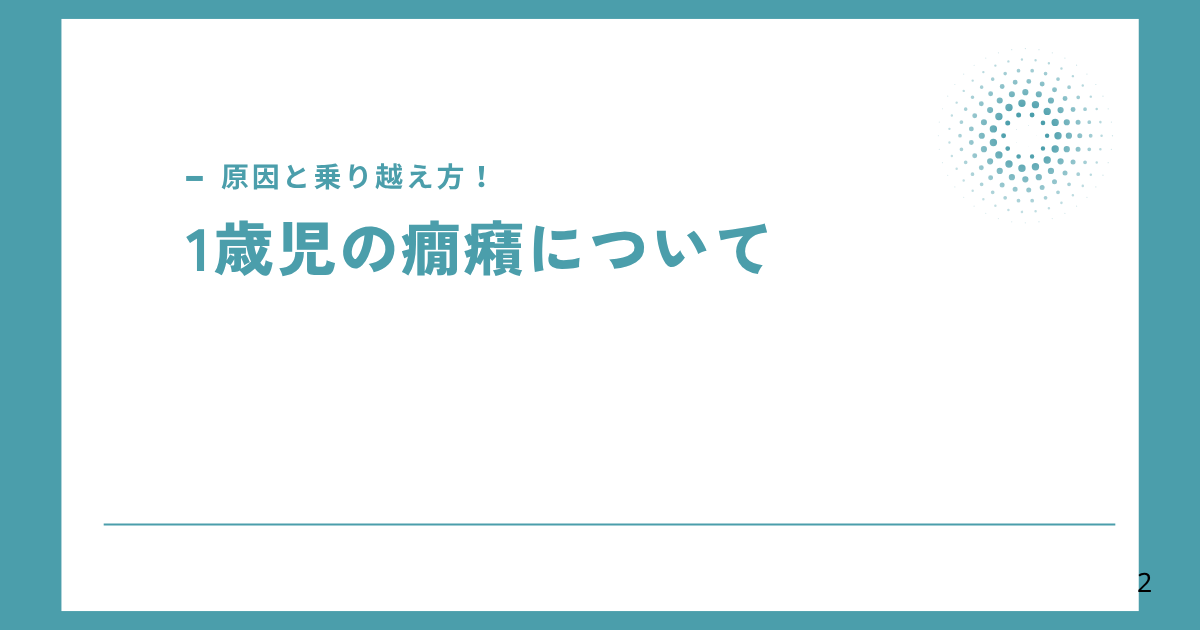
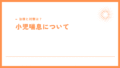
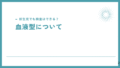
コメント