生後6ヶ月を過ぎると、赤ちゃんの成長は目覚ましく、日々新しい発見の連続ですよね。特に生後9ヶ月前後って、「あれ?こんなこともできるようになったの!?」なんて驚きがたくさんある時期ですね。大人の真似っこも上手になってきて、「パチパチ」と拍手したり、「バイバイ」と手を振ったりする姿は、本当に可愛くて、思わず動画を撮ってしまいます。
今回は、そんな赤ちゃんの「バイバイ」「パチパチ」はいつから始まるのか、もし「うちの子、まだしないけど大丈夫?」って不安に感じているパパ・ママのために、練習の必要性や発達との関係についても詳しく解説していきます。
赤ちゃんが「バイバイ」「パチパチ」し始めるのはいつから?
赤ちゃんが「バイバイ」や「パチパチ」といった仕草を見せ始めるのは、一般的に生後9〜10ヶ月頃が目安です。もちろん個人差があるので、早い子だと生後7〜8ヶ月頃から見られることもあります。
この時期の赤ちゃんは、大人の真似をすることにめちゃくちゃ興味津々です。 パパが仕事に行くときに、パパやママが「いってらっしゃい!」って手を振る様子を見て、ぎこちなく手を左右に振ってみたり、パパやママが楽しそうに手を叩くのを見て、一生懸命両手を合わせてパチパチ拍手をしたりします。
生後9〜10ヶ月頃は、ハイハイからつかまり立ちへと身体的な成長もぐんぐん進む時期ですが、脳の発達も驚くほど進んでいます。「あ、ママが手を振ってる」「パパがパチパチしてる」って、聞いたことや目で見たことを自分で表現しようと頑張っているんです。言葉も少しずつ理解し始めるので、できることがどんどん増えて、これまで以上に赤ちゃんとのコミュニケーションが楽しくなります。
我が子も10ヶ月頃から、パチパチができるようになり、大人の真似をすることが増えました。
赤ちゃんが「バイバイ」「パチパチ」しないときって練習は必要?
「うちの子、もう10ヶ月過ぎたけど、まだバイバイもパチパチもしない…」って、ちょっぴり心配になるパパ、ママもいるかもしれません。でも、この時期の子供の成長には個人差がとっても大きいので、心配しすぎる必要は全くありません。
もしかしたら、赤ちゃんがバイバイやパチパチする瞬間を、パパやママが見逃しているだけなんてこともあります。特別な練習を無理強いする必要はありませんが、赤ちゃんの好奇心をくすぐるような、ちょっとしたきっかけ作りをしてあげるのはとっても効果的です。
1. 普段の生活で「バイバイ」する仕草を見せてみる
日常生活や遊びの中で、自然な形で「バイバイ」のきっかけを作ってあげましょう。
- パパが仕事に行くとき:「パパ、いってらっしゃ〜い」って、ママが赤ちゃんの腕を持って一緒に手を振ってみる。
- 一人遊び中に目が合ったら:ふと赤ちゃんがパパ、ママを見たときに、「〇〇ちゃん、バイバイ」って優しく声をかけながら、手を振ってコミュニケーションをとってみる。
こんなちょっとした声かけや動きの積み重ねが、赤ちゃんにとっては大きな学びになります。
2. 何かできたら「パチパチ」と拍手してあげる
赤ちゃんが何か新しいことができた時、「できたね!すごいね!」って声をかけながら、思いっきり「パチパチ」と拍手してあげましょう。
「パチパチ」は、嬉しいときや褒めたいときに使う仕草なんだよ、って言葉や感情と一緒に教えてあげることで、赤ちゃんも少しずつ「あ、これって嬉しい時にするやつだ」って理解していくようになります。
3. 音楽に合わせて手拍子もおすすめ!
「しあわせなら手をたたこう」など、手遊び歌を交えた童謡に合わせて、パパやママが楽しそうに手拍子する姿を見せてあげましょう。音楽のリズムに合わせて手を叩くのは、赤ちゃんにとっても楽しい遊びになりますよ。
パパやママと一緒に「パチパチ」と手を叩く感触を楽しむことで、親子のコミュニケーションも深まりますし、赤ちゃんも「手を叩くのって楽しいな!」って感じてくれるはずです。
赤ちゃんが「バイバイ」「パチパチ」しないのは発達の影響?
生後9〜10ヶ月を過ぎた赤ちゃんが「バイバイ」や「パチパチ」をしないと、「もしかして発達の遅れなのかな…?」って不安に感じるパパ、ママもいるかもしれません。でも、先ほどもお伝えした通り、この時期の成長は本当に個人差が大きいんです。
大人と同じように、積極的な子もいれば、ちょっと恥ずかしがり屋さんな性格で、なかなか人前で仕草を見せない子もいます。無理強いはせず、焦らず、赤ちゃんのペースに合わせて、パパやママが優しく促してあげることが大切です。
また、「バイバイ」や「パチパチ」をしないことが、そのまま自閉症や発達障害と断定できるわけではありません。あくまで赤ちゃんの個性の一つとして捉えることが大切です。
ただし、
- あまり目を合わせない
- 表情が乏しい
- パパやママの呼びかけと全く違う行動をする(言葉を理解していないように見える)
といった他の兆候が多く見られ、どうしても気になるようであれば、念のため専門家(小児科医や発達相談窓口など)に相談してみるのも良いでしょう。
まとめ
赤ちゃんの月齢が低い時期は、どうしても他の子と比べてしまいがちですよね。「あの子はもうバイバイしてるのに…」「うちの子はまだパチパチしない…」なんて思うこともありますよね。
でも、成長がゆっくりな子も、ぐんぐん進む子も、それはその子の大切な個性です。焦らず、赤ちゃんのペースに合わせてあげましょう。
赤ちゃんって、今日できなかったことが、明日になったら突然できているなんてこともザラにあります。「昨日までハイハイだったのに、今朝起きたらつかまり立ちしてた」なんて経験、している方もいるのではないでしょうか。
一つ一つの動作だけに注目するのではなく、まずは赤ちゃん自身の心身の成長全体を温かい目で見守ってあげてください。
もし、全体的な成長を見て「やっぱり気になるな…」という点があれば、1歳児健診のタイミングでかかりつけ医や保健師さんに相談できるよう、普段の様子をメモしておくのがおすすめです。具体的なエピソードがあると、より的確なアドバイスをもらいやすくなります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

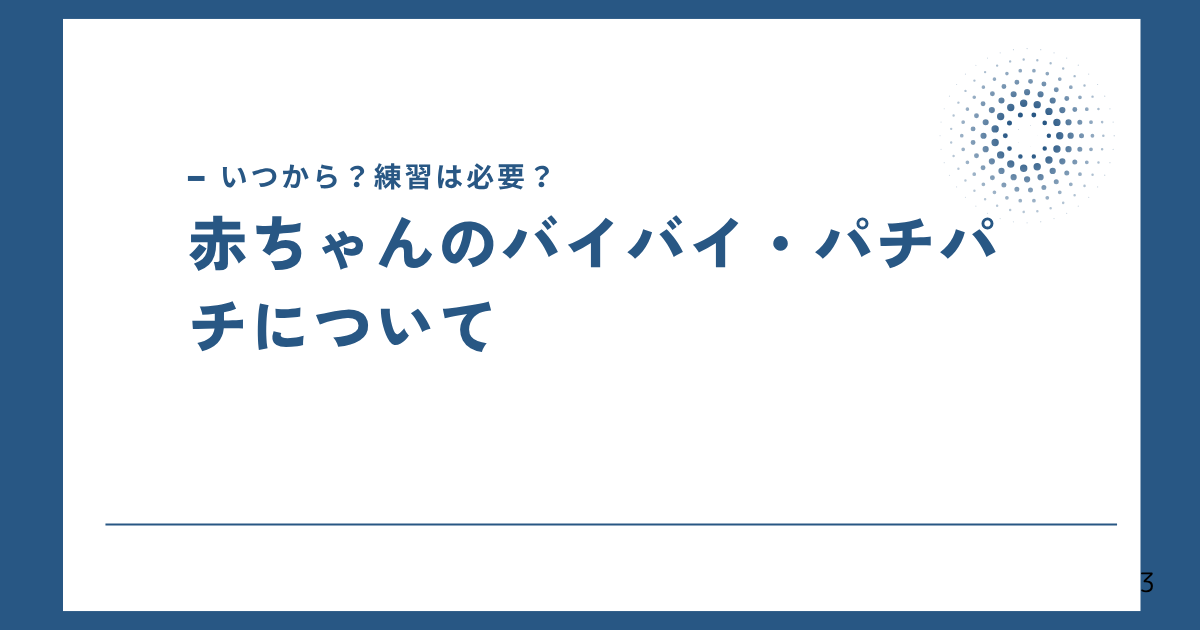
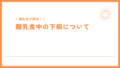
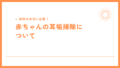
コメント