赤ちゃんが咳が長引いたりすることありますよね。風邪なのか分からなかったり、咳していて辛くないのかと心配になるかと思います。
今回は、赤ちゃんが咳が長引く原因や対処法、病院受診について紹介したいと思います。
赤ちゃんの咳が長引く原因は?
咳は喉や鼻に入った異物を外に出そうとする反射的な行動の一つです。
赤ちゃんの場合は空気の通り道が狭く、寒暖差や乾燥、小さな異物にも反応しやすいために、大人よりも咳をしやすいといわれています。
肺炎
肺炎は、ウイルスや細菌が肺に感染して起こる病気です。
咳と高熱が続き呼吸困難・顔色不良がある場合は、肺に炎症が起きている可能性もあります。
ただし、熱が高くなくても、顔色が悪く呼吸が苦しそうな時や、短い間に何度も激しく咳をしている時は、すぐに病院を受診しましょう。
気管支炎
ウイルスや細菌による感染が原因で気管支に炎症が起きます。発熱・咳・鼻水をともない、風邪が悪化してかかることがあります。
「コンコン」という乾いた咳が、次第に「ゴホゴホ」という痰のからんだ音になり、発熱やのどの痛みを伴います。
母乳やミルクを飲む力が低下したり、呼吸困難になることもあるので注意しましょう。
小児喘息
「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)が聞こえるような状態のときは、小児喘息の可能性があります。
深夜や早朝に咳の発作が起こりやすいのが特徴です。ダニやペットなどのアレルゲン、タバコの煙などの気道を刺激させる物質で症状が悪化します。
小児喘息は重症化すると呼吸困難を起こし、命にかかわることもあります。しかし、早めに診断され適切な治療を受ければ、成長とともに良くなっていくことが多いです。
百日咳
百日咳は、咳、鼻水、くしゃみから始まり、顔を赤くして咳き込む発作が3ヶ月近く続くこともあります。発熱がないことが特徴です。
五種混合ワクチンを接種する前の赤ちゃんには百日咳の免疫がないので、新生児でもかかることがあります。
クループ症候群
2歳~6歳くらいのお子さんに多くみられる病気です。
「ケンケン」と犬が吠えるような咳が出るときは、のど(喉頭)の少し奥にある声帯あたりが炎症するクループ症候群かもしれません。
夜間や早朝に悪化することがあり、突然呼吸困難を起こすことがあります。そのようなときは、自己判断で市販の風邪薬や咳止め薬を飲ませることはせず、救急で病院を受診しましょう。
赤ちゃんの咳が止まらないときの対処法とは?
鼻水をこまめに取る
鼻水が出ている場合、鼻水が喉に落ちて気管をふさいでしまい、咳が出ることもあります。
鼻水吸引器でこまめに吸って鼻水をとってあげましょう。
部屋を加湿する
空気が乾燥すると、のどが刺激され咳が出やすくなるので、「加湿器を使う」「濡らしたタオルを部屋に干す」などして、部屋の湿度を60%程度に保つようにしてください。
ただし、加湿器はカビの温床となりやすいのでこまめに手入れをしましょう。
部屋の環境を整える
ホコリや乾燥はアレルギー症状やぜんそくなどの長引く咳にもつながることがあります。部屋の掃除や換気をしたり、空気清浄機を使ったりして部屋を清潔に保ちましょう。
水分を多く摂る
喉を直接潤すことも大切です。喉を刺激しないように常温の水やお茶、母乳やミルクなどで水分を多く摂らせてあげましょう。
上体を高くする
夜中に咳がひどくなり眠れない時は、腰や背中にクッションなどを当て、上体を起こしてあげると少しラクになります。また、枕の高さを調節して気道を確保すると楽になることもあります。
赤ちゃんの咳が止まらないときの受診する目安は?
子どもが咳をしていても、元気で食欲があれば、まず問題ありません。しかし、一般的な風邪であっても、寝苦しくて夜中に何度も目が覚めてしまう、咳き込んで母乳やミルクが飲めないといった場合は、すぐに病院を受診してください。
咳が長く続くだけでなく、赤ちゃんの様子に次のような症状が見られたときは、夜間救急外来など時間外でも診察してくれる病院か、子ども医療電話相談(#8000)に電話で相談しましょう。
時間外でも受診が必要な状態
● 「ゼーゼー」「ヒューヒュー」など、喘鳴のある発作がある
● 「ケン、ケン」と、犬の遠吠えのような異常な咳が出ている
● 咳のたびに肋骨の間や鎖骨がへこむような呼吸困難をおこしている
● 酸素不足で顔面やくちびるが青くなっている
● ぐったりして意識障害が見られる
● 水分が摂れず、おしっこが出ていない
まとめ
前述したとおり、基本的に元気で食欲があれば問題ないですが、夜何度も起きてしまうなどいつもと違う様子のときは、早めに病院受診するのが良いでしょう。
特に冬の時期は空気が乾燥するためより咳が出やすくなるため、部屋の環境などを整えるようにしましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

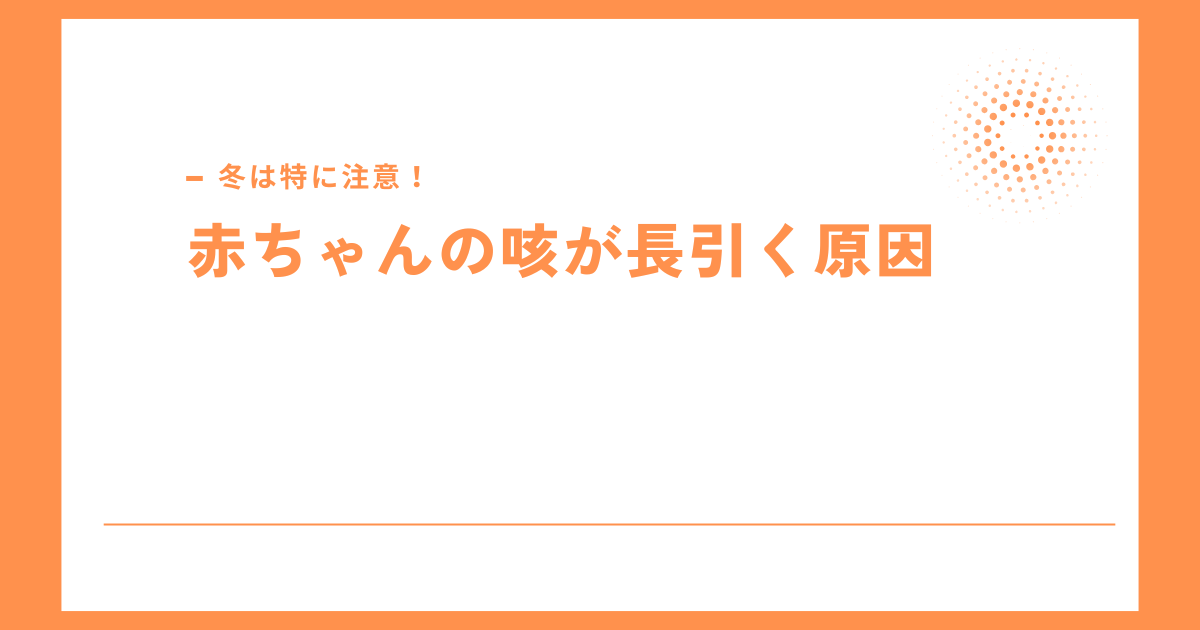
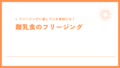
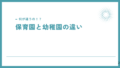
コメント