「うちの子、いつまでお昼寝させるべき?」と悩んでいるパパ、ママもいるのではないでしょうか。
赤ちゃんだった頃は「お昼寝タイム」をしっかり確保していたけど、子どもが成長するにつれて、「お昼寝が長すぎ」、「夜寝なくなるのはお昼寝のせい?」、「周りの子はもうお昼寝してないみたい」などの疑問や焦りが出てきたりすることもあるかもしれません。
この記事では、「幼児のお昼寝の疑問」を解決したいと思います。
幼児のお昼寝はいつまでさせるべき?
結論から言うと、幼児がお昼寝をするのはおおよそ3〜4歳までが目安です。
早い子だと2歳半で卒業、遅くても5~6歳の就学前にはお昼寝をしなくなる子が多いようです。
これは「何歳になったら絶対やめる!」と決まっているわけではなく、
- 生活リズムの変化(習い事や園生活など)
- 体力の向上(昼間に寝る必要がなくなる)
といった要因で、自然と卒業していくものなんですね。
お子さんの「眠たい」というサインと、日中の様子をしっかり観察して、無理のない卒業を目指しましょう。
幼児のお昼寝、保育園ではいつまで?
保育園では何歳までお昼寝させるのか気になりますよね。
保育園ではお昼寝を「午睡(ごすい)」と呼びますが、実は厚生労働省で明確な年齢は定義されていません。
「一人一人の生活のリズムに応じて、安全な環境の下で十分に午睡をする」という指針があり、各園の判断に任されています。
現状を見ると、多くの保育園では、
- 4歳児クラス(年中)
- 5歳児クラス(年長)
からお昼寝をさせない(または希望者のみ)園が多いようです。
もし、「うちの子は体力があるからもう不要かも?」と感じたら、保育士さんに相談してみるのも一つの手です。
幼児のお昼寝をやめさせる必要はあるの?
「夜寝ないからお昼寝をやめさせた方がいい?」と悩む方もいますが、無理にやめさせる必要はありません。
大人だって、ご飯を食べた後の午後1~3時くらいは眠くなるのと同じで、子どもはさらに体力がないので、「足元がフラフラしているとき」「機嫌が急激に悪くなっているとき」は、まだお昼寝が必要なサインです。
眠いのを無理に我慢すると、脳の働きが鈍くなり、怪我や事故につながることも考えられます。
ただし、夜の睡眠に影響が出ないように、次のポイントを意識しましょう
お昼寝のベストな時間と長さ
長さ:1〜2時間(長くても3時間まで)
終了時刻:午後3時くらいまでには切り上げる
お昼寝が長すぎたり、夕方にずれ込んだりすると、確実に夜の寝つきが悪くなります。逆算して、お昼寝の時間と長さを調整してみてください。
幼児のお昼寝を上手に卒業させるには?
「そろそろ卒業させたいな」と思ったときに、まず試してほしいのが「夜の睡眠を充実させること」です。
お昼寝卒業の鍵は、1日に必要な睡眠時間を夜にしっかり確保してあげること。
| 年齢 | 1日に必要な睡眠時間(目安) |
| 1〜2歳 | 11~14時間 |
| 3〜5歳 | 10~13時間 |
※これはアメリカの研究結果なのであくまで目安ですが、参考になります。
例えば3歳で11時間寝かせたい場合、朝7時に起きるなら夜8時には寝かしつける必要があります。
ちょっと夜更かしかもと感じたら、まずは就寝時間を30分〜1時間早める努力をしてみると良いでしょう。
夜にしっかり眠ることで、日中も元気に過ごせるようになり、自然と「昼間に寝る必要がなくなる」という流れが作れます。
卒業までのステップ
- 夜の睡眠時間を確保する: 就寝時間を早め、規則正しい生活を送る。
- 日中の活動量を増やす: 公園で遊ぶ、習い事を始めるなど、体をしっかり動かす。
- 徐々に減らす: 急にやめずに、お昼寝の時間を「1時間半 → 1時間 → 30分」と徐々に減らしていく。
- 「横になる時間」に切り替え: お昼寝をしない日でも「静かに絵本を読む」「ゴロゴロする」といった休息タイムを設けて体を休ませる。
もし、夕方の中途半端な時間に眠くなったり、夕食時に機嫌が悪かったりする場合は、まだお昼寝が必要なサインです。焦らず、お子さんのペースに合わせてあげましょう。
まとめ
お昼寝をいつまで続けるかは、お子さんの成長と生活リズムに合わせて調整してあげてください。
無理にやめさせようとするよりも、夜に質の良い睡眠をしっかり取らせることが、自然な卒業への一番の近道です。
小学生になれば、生活が一変してお昼寝は卒業します。就学前を目安に、親子で一緒に無理なくお昼寝を卒業していきましょう。
お子さんの状況次第で臨機応変に対応してあげてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

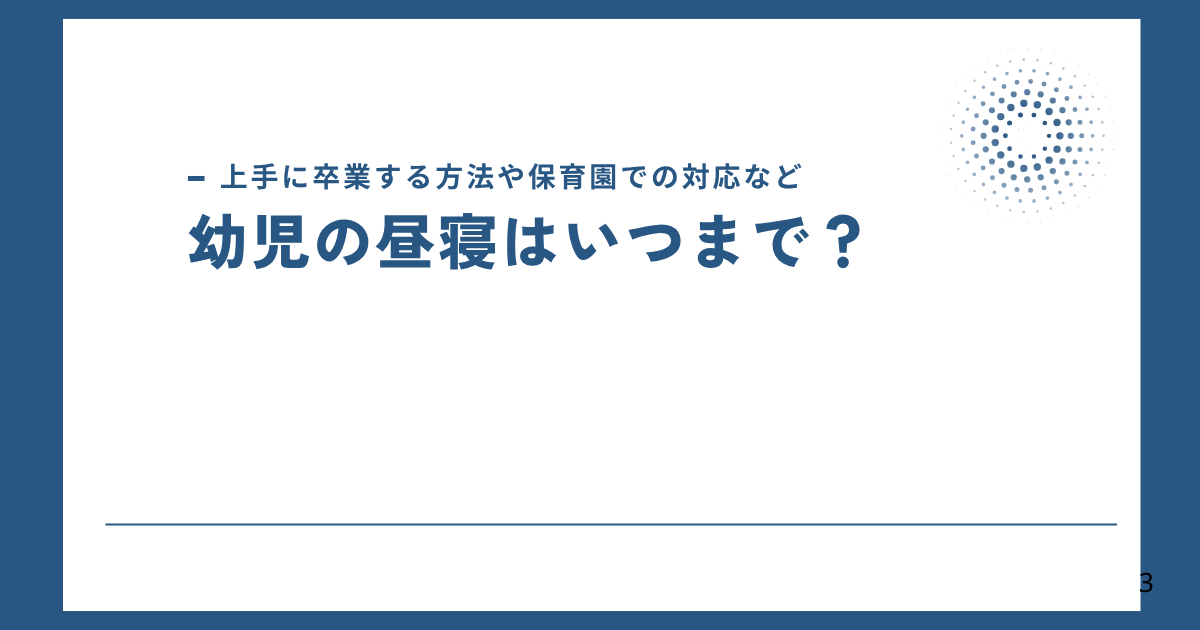
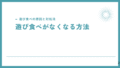
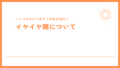
コメント