ホッピング反応について、初めて聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、赤ちゃんの成長過程で大切な反射のひとつです。
今回は、「ホッピング反応ってなに?」「出ないと成長に影響あるの?」など、親として気になるポイントをわかりやすくまとめてみました。
ホッピング反応ってどんな動き?
簡単に言うと、赤ちゃんが倒れそうになったときに、足で踏ん張って体勢を立て直そうとする反応のことです。
たとえば大人も、立っていて前にグラッときたら、自然と一歩前に出ますよね。これと同じような動きが赤ちゃんにも出てきます。
実際に確認する方法としては、赤ちゃんを立たせて前に倒すと、片足を前に出してバランスを取ろうとするか 後ろや左右に倒したときも、それぞれの方向に応じて足で支えようとするか
この動きが見られれば「ホッピング反応あり」となります。
いつごろから見られるの?
ホッピング反応は、生後15〜18ヶ月ごろにはっきりと見られるようになると言われています。でも、個人差があるので早い子は9〜10ヶ月くらいから兆しが出てくることもあります。
実際、9〜10ヶ月健診では、ホッピング反応のチェックがされることもあります。
ホッピング反応が出ないとダメ?
結論から言うと、ホッピング反応が出ない=すぐに問題がある、というわけではありません。
特に生後9〜10ヶ月の段階では、倒れる方向のうち1つでも反応があればOKとされています。
「うちの子、まだ出てないかも…」と焦らなくて大丈夫です。つかまり立ちのように、出る時期には個人差があります。
また、健診ではホッピング反応だけでなく、赤ちゃんの全体的な発達を見て総合的に判断されます。心配なことがあれば、その場で相談すればOKですよ。
ホッピング反応と似ている「パラシュート反応」とは?
ホッピング反応とセットで語られるのが「パラシュート反応」。
これは赤ちゃんが前に落ちそうになったとき、両腕を前に出して支えようとする動きのこと。まるでパラシュートを開くような仕草なので、こんな名前がついています。
低い位置での反応 → 生後8ヶ月ごろ〜
高い位置での反応 → 生後9〜10ヶ月ごろには多くの赤ちゃんに見られます
ただし、怖がりさんだったり、緊張しやすい子だとこの反応が出にくいこともあります。これも、ほかの発達が順調なら特に問題なし。
9〜10ヶ月健診でチェックされるその他のポイント
ホッピング反応やパラシュート反応以外にも、健診では次のようなことを見ています。
つかみ方に異常がないか
小さなビーズやビー玉などをつかませて、指先の動きをチェック。不自然につかんだり、ぎこちない動きがあると注意が必要になることも。
つかまり立ちができるか
イスやパパ、ママに手をかけて立ち上がろうとする様子があるかを見ます。少しの時間だけでもOK。
ハイハイができるか
お腹をつけた「ずりばい」や、手足を交互に動かす「ハイハイ」ができるかをチェック。ただし、ハイハイせずに立っちゃう子もいます。
愛着の形成
パパやママがそばにいるときと、離れたときの赤ちゃんの反応を見て、安心感(愛着)が育っているかを確認します。
赤ちゃんの反応は“今”だけじゃわからないことも
ホッピング反応に限らず、赤ちゃんの発達って本当に個人差だらけ。
でも、ある日突然スイッチが入ったかのように新しい動きを見せてくれたりするんです。健診はあくまで「今の成長の目安」。過度に心配しすぎず、日々の中でちょっとずつ変化を楽しんでいく気持ちが大事なんじゃないかなと思います。
まとめ
ホッピング反応は、倒れそうになったとき足で体を支えようとする反射です。
生後15〜18ヶ月ごろにはっきり現れることが多いです。9〜10ヶ月健診で兆しがあるかを見る場合も、出ていなくても他の発達と総合的に判断するので、気にしすぎなくてOKです。
赤ちゃんの発達はマイペース。それを見守る私たち親も、あたたかく、のんびり構えていきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

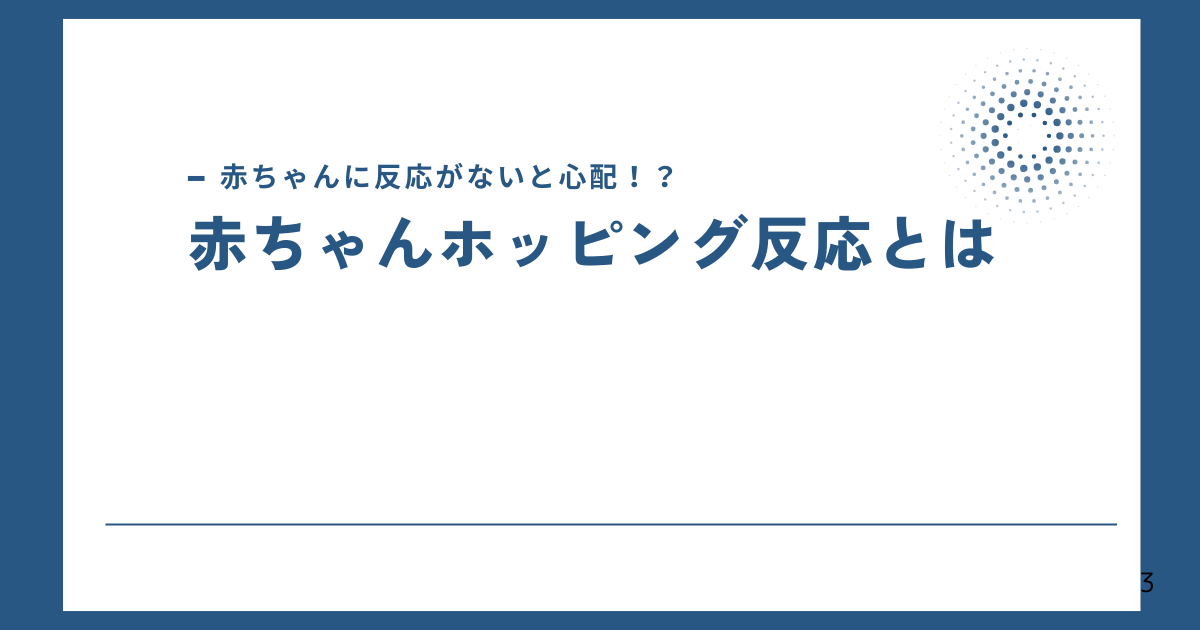
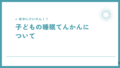
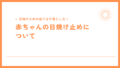
コメント