1歳半〜4歳頃まで続く、長〜い戦いであるイヤイヤ期。
毎日のように理由もなく泣きわめき、床にひっくり返るわが子を前に、「いつまで続くの!」と頭を抱えてしまうパパ、ママは多いはずです。
特に「1歳のイヤイヤ」と「2歳のイヤイヤ」は、原因も対応策も全く違います。同じやり方で対応しても、イライラが募るばかりです。
そこで今回は、「イヤイヤ期とは何?いつからいつまで続く?」「【1歳と2歳】で対応策はどう変えるべきか?」について、解説したいと思います。
イヤイヤ期とは?「魔の2歳児」と呼ばれる理由と成長の関係
何かにつけて「イヤ!」「自分でやる!」と自己主張し、思い通りにならないと泣きわめいたり、時には暴れたりするのがイヤイヤ期です。
これは「ワガママ」ではなく、子どもが自我に目覚め、心の成長を遂げている証拠です。これまで受け身だった子どもが、「自分」という存在を認識し、「これがしたい」という意思を持ち始めたのです。
しかし、この時期の子どもは、自分の「したい」を言葉でうまく伝えられない、「したい」という気持ちと「できる」能力に大きなズレがあるというジレンマを抱えています。
この心の葛藤やもどかしさが、「イヤイヤ」という形で爆発してしまうのです。親にとっては大変ですが、立派な成長のステップと捉えましょう。
イヤイヤ期はいつからいつまで続く?
イヤイヤ期が始まる時期、終わる時期には個人差がありますが、一般的には以下の通りです。
開始時期:1歳半〜2歳頃(言葉が増え始める時期)
ピーク:2歳〜3歳頃(「魔の2歳児」と呼ばれる)
終息:3歳になる頃に落ち着き始め、4歳になる頃にはほとんど終わる
「4歳を過ぎても続いた」というケースもありますが、いずれは必ず落ち着きます。永遠に続くわけではないと心に留めておくことが、パパ、ママのメンタル維持に繋がると思います。
【1歳のイヤイヤ期】対応を変えるコツ
1歳半頃から始まるイヤイヤ期は、まだ自己主張がそこまで強くなく、「これがしたい」という気持ちが瞬間的に出てくるのが特徴です。
言葉で伝える能力が極めて低いため、そのもどかしさからのイライラが目立ちます。
1歳イヤイヤ期の対応策:
1歳のイヤイヤ期は、基本的に「別のものに興味をそらす」ことで対処しましょう。
- やりたいことを危険がない範囲でとことんやらせる「汚れる」「時間に遅れる」などの不安はひとまず置いて、身に危険がなければ「今は子どもの自立のための時間」と考えて見守ってあげてください。事前に時間に余裕を持つ工夫が大切です。
- 別のものに興味をそらす1歳児は目の前のことへの強いこだわりがまだ薄いため、代替案が効果的です。
- 例:「(白い服は)イヤ!」→「じゃあ、青い服にする?それともピカピカの赤い服にする?」
【2歳のイヤイヤ期】対応を変える“唯一のコツ”
2歳になると、「これがやりたい!」という欲求が具体的になり、身体能力も精神発達も進むことで「自分の意思を貫きたい」という気持ちが非常に強くなります。
イヤイヤも本格化し、別のものにそらしても効果がないことが増えます。
2歳イヤイヤ期の対応策:
2歳のイヤイヤ期は、「子どもの気持ちを代弁し、できることは最後まで見守る」姿勢が大切です。
- 何がしたいかを聞き続ける or 気持ちを代弁する:「これが取りたかったの?」「お風呂に入るのがイヤなんだね?」と、子どもの気持ちを親が言葉にしてあげることが重要。「伝わった」という満足感が、落ち着きに繋がることがあります。
- 自分で解決できるようになるまで待つ:やりたいことが上手くできず、苛立ちからイヤイヤが始まることがあります。この場合は、親が手伝うとさらに癇癪を悪化させることも。親はグッとこらえて、「失敗してもいいよ」「見守っているよ」というサインを送りながら、子ども自身が解決するまで待ってあげましょう。
- 【危機回避のための提案】「どちらがいい?」で選択肢を与える:どうしても譲れないルール(例:公園から帰る時間)には、「AとB、どっちがいい?」と、子どもが自分で選んだという満足感を与えましょう。
- 例:「もう帰ろうね」→「この道で帰る?それともあっちの道で帰る?」
まとめ
「いい加減にしなさい!」と怒鳴りたくなったり、自己嫌悪に陥ったりすることもあるでしょう。
しかし、イヤイヤ期は子どもが精神的に自立するための重要なプロセスであり、必ず終わりが来ます。
「もう我慢できない…」と心が折れそうなときは、家事代行サービスで掃除や料理の負担を減らし、心の余裕を作る、ミールキットで献立を考えたり調理する時間を短縮し、子どもとの時間に充てる。など、外部の力を借りて自分の心を守ることが大切です。パパ、ママの笑顔が、子どもの安心感に繋がります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

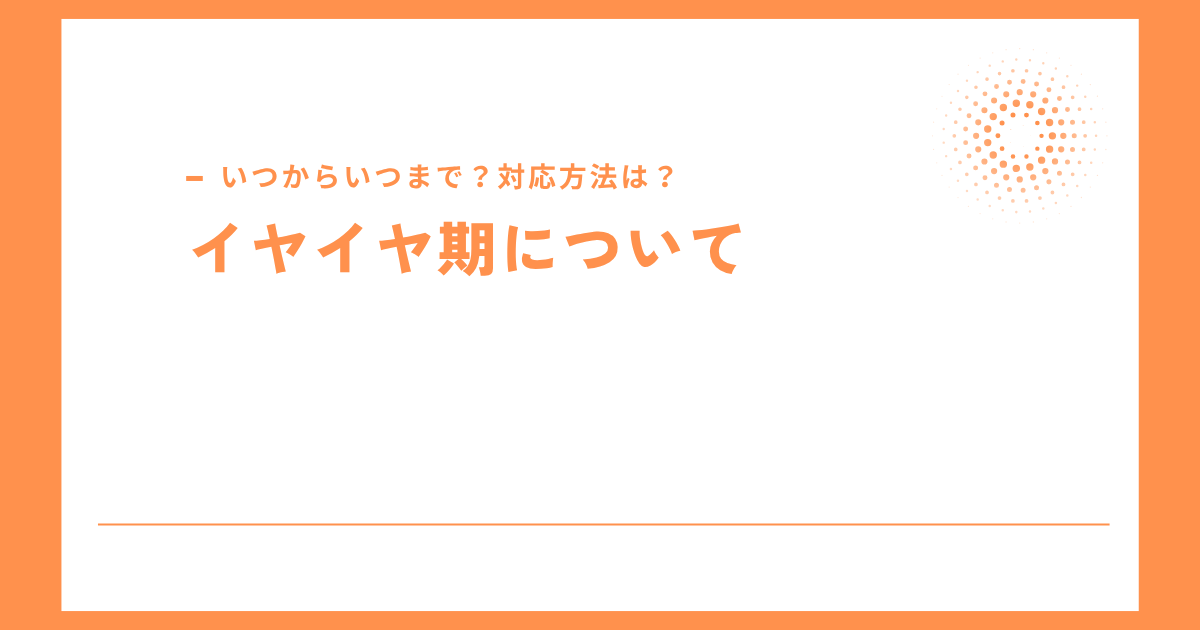
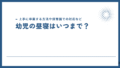
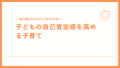
コメント