「食育」って言葉、よく聞くけど具体的に何をしたらいいの?
離乳食も進んで、いよいよ幼児食。「ちゃんと栄養のあるものを食べさせなきゃ」って焦るパパ、ママも多いんじゃないでしょうか。
正直、最初はケンターンも、「食育=バランスの取れた食事」くらいにしか思っていませんでした。でも、食育の本質はそこじゃない!
「食べることは楽しい!」と感じ、「何を食べるか自分で選べる力」を育むことこそが、子どもの心と体の土台を作ります。
この記事では、子どもの食育の「なぜ?」から、家庭で今すぐできる具体的な方法、ステップアップに役立つ資格まで解説したいと思います。
そもそも、子どもの「食育」って何?目的は?
まず、食育の定義からです。
国が定めた食育基本法によると、食育とは「様々な経験を通じて『食』に関する知識と『食』を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てること」です。
要は、
- 「食べるって楽しい!」と思える心
- 「体に良いものを選べる」判断力
- 「感謝して食べる」マナーや習慣
この3つを子どものうちに身につけて、心も体も健康な大人になってもらおうという国の取り組みです。
食育が必要な2つの理由
なぜ今、食育が必要とされているのでしょうか。その理由としては2つあります。
1. 栄養の偏りや生活習慣病の低年齢化
現代は、ファストフードやコンビニの惣菜など、「すぐに食べられるもの」が簡単に手に入ります。便利ですが、その結果、栄養の偏りや肥満など、食生活の乱れからくる健康問題が低年齢化しています。
「何を食べるか」を意識しないと、子どもの成長に大きな影響が出てしまうんです。
2. 「孤食」や「個食」によるコミュニケーション不足
共働きや習い事で忙しい家庭では、子どもが一人で食べる「孤食」や、家族で食卓を囲んでもそれぞれ違うものを食べる「個食」が増えています。
これは、食事のマナーを学ぶ機会が減るだけでなく、「家族のコミュニケーション」が失われる大きな原因にもなります。
食育は、ただ栄養の話をするだけじゃなく、「家族で楽しく食卓を囲む」という温かい体験を通じて、子どもの心を豊かに育むためにも欠かせないものです。
食育はいつから始めるべき?遅すぎることはない!
結論から言うと、食育を始めるのに「遅すぎる」ということはありません。
特別なルールもないので、日々の生活の中で自然と取り入れていくのが一番大事です。
パパ・ママの姿を見せる「胎教」の時期から!
赤ちゃんは離乳食を始める前から、パパとママが食事をする姿をよーく見ています。
- 「美味しいね」と笑顔で食べる
- 「いただきます」「ごちそうさま」を言う
- 家族で楽しそうに会話する
大人が「食べることは楽しい!」という姿勢を見せるだけで、それは立派な食育です!
【成長時期ごとのポイント】
| 時期 | 食育のゴール | 家庭でできること |
| 離乳食期(5〜1歳半頃) | 「食べる楽しさ」を知る | 様々な食材の味・舌触りに慣れさせる |
| 幼児食期(1歳半〜6歳頃) | 「マナーと自立」を学ぶ | 「こぼさずに食べる」「残さず食べる努力」など基本的なマナーを教える |
| 学童期(小学生以降) | 「知識と選択力」を育む | 献立を一緒に考える、食べ物の栄養について教える |
子どもの成長に合わせて、少しずつステップアップしていけばOKです。
今すぐできる!子どもの食への興味を引き出す方法5選
食育は、何も特別な料理教室に行く必要はありません。家庭で、遊び感覚でできることから始めましょう。
以下の方法を試しながら、食ベものへの興味を持たせて、食の喜びを一緒に共有しましょう。
1. 親子で「お買い物探検隊」に出かける
ネットスーパーも便利ですが、たまには子どもと一緒にスーパーや商店街へ足を運びましょう。
「今日のお肉は何からできてる?」 「このトマトはどこでできたのかな?」
こんな風に、食材を「説明しながら」買い物をします。食材の種類、栄養、産地などを教えることで、いつものメニューが何でできているのか、子どもは興味を持ち始めます。
レジに並ぶ時も「このお野菜、カゴに入れてくれてありがとう!」って褒めれば、子どもの「役に立った!」という気持ちも満たされます。
2. 小さな「家庭菜園」で命を学ぶ
マンションでもベランダでできるミニトマトやキュウリなどの簡単な野菜を親子で育ててみましょう。
- 種をまく
- 水をあげる
- 実がなるのを観察する
- 自分で収穫して食べる
この一連の体験は、「食べ物は命をいただいている」という感謝の気持ちや、食材を大切にする心を育みます。
子どもが自分で収穫した野菜は、苦手でも「食べてみようかな?」という気持ちになりやすいです。
3. 「遊び感覚」で親子クッキング
料理は最高の食育です!包丁を使わない簡単な作業からお手伝いしてもらいましょう。
- レタスやキャベツをちぎる
- ご飯を握る(おにぎり)
- 卵をかき混ぜる
「自分で作ったもの」は特別な味がします。遊び感覚で料理に関わることで、達成感が得られ、食べ残しが減るという嬉しい効果もあります。
慣れてきたら、安全な子ども用包丁を準備して、簡単な食材カットに挑戦させてみましょう、
4. テレビを消して「会話のある食卓」を囲む
「いただきますは皆が揃ってから」「全員が食べ終わってからごちそうさま」
まずは、家族が揃って食事を始める習慣をつけることが大切です。食事中はテレビを消して、家族間の会話を楽しみましょう。
- 「今日のご飯、何が美味しい?」
- 「このお野菜はシャキシャキだね!」
食べ物の感想を言い合うことで、味覚のトレーニングにもなりますし、家族のコミュニケーションも深まります。これが、最も簡単で効果的な食育かもしれません。
5. 食育の「絵本」で楽しく学ぶ
食べ物や料理をテーマにした絵本を読むことも、食の大切さを学ぶ良い機会です。
絵本なら、苦手な野菜も可愛いキャラクターになって登場したり、料理の楽しさを想像力を掻き立てながら教えてくれます。
親子でお気に入りの絵本を探して、読み聞かせの時間に取り入れてみましょう。
まとめ
食育は、すぐに結果が出るものではありません。
イヤイヤ期で食べ物を投げたり、食事中に立ち上がったり…食育どころじゃない日も当然あります!
でも、大丈です。
パパやママが美味しそうに食事をする姿や、楽しそうに料理をしている様子を子どもが見るだけでも、それは最高の食育です。
子どもが大きくなるにつれて、家族で食事をする時間も少しずつ減っていくものです。
「親子で食事ができる貴重な時間」を大切にして、まずは「食を楽しむ」ことから始めていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございます。

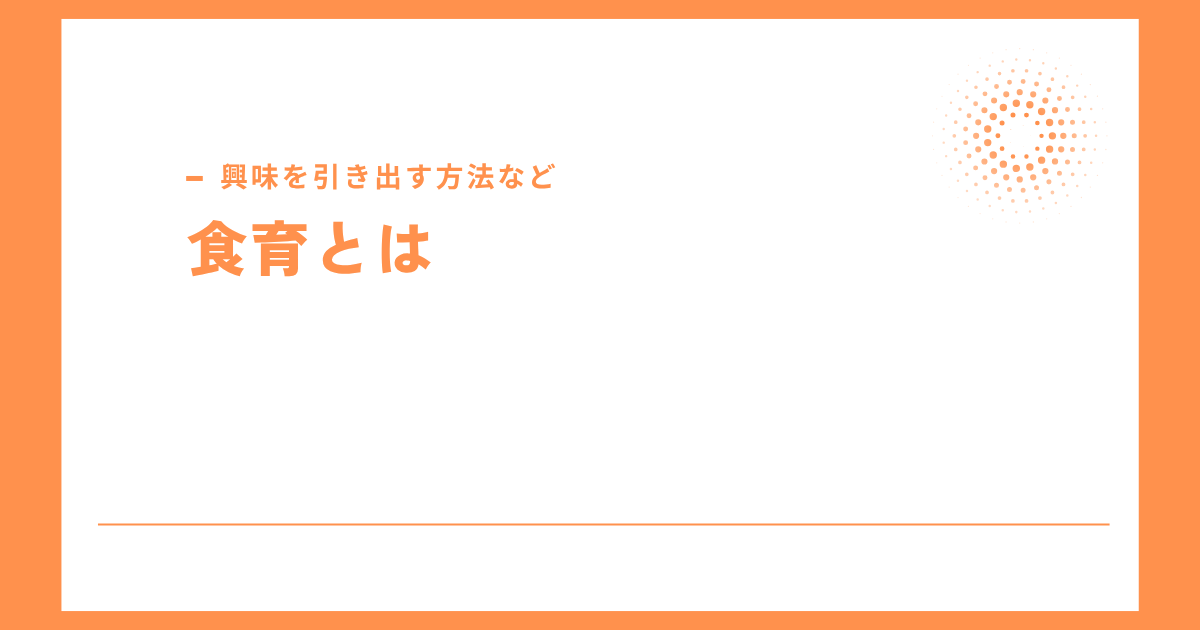
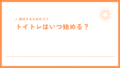
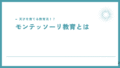
コメント