「おたふくかぜ」と聞くと、子どもがかかりやすい病気の一つという印象を持つ人が多いのではないでしょうか。
「おたふく」という可愛らしい名前から、そこまで心配しなくていい病気だと思われがちです。
でも実は、子どもの人生を左右するような後遺症を残す可能性がある、ちょっと怖い病気なんです。
今回は、おたふくかぜの予防接種について紹介していきます。
おたふくかぜってどんな病気?
おたふくかぜとは、ムンプスウイルスに感染することで、耳の下にある「耳下腺」や「顎下腺」が炎症を起こす病気です。
正式には「流行性耳下腺炎」というのですが、耳の下が腫れておたふくのお面みたいになることから、この名前で呼ばれています。
感染力が非常に強く、特に3〜6歳の子どもがかかりやすいのが特徴です。
もし感染して耳の下が腫れると、
- 口を開けたり
- 固いものを噛んだり
する時に痛みが生じます。
通常は1週間ほどで腫れや痛みは治まりますが、注意が必要なのは合併症です。
おたふくかぜは、軽い病気だと思われがちですが、まれに
- 髄膜炎
- 脳炎
- 難聴
- 膵炎
など、さまざまな合併症を起こし、後遺症を残すことがあります。
特に「髄膜炎」の合併は10〜100人に1人の割合でみられるとされていて、決して珍しいことではありません。
おたふくかぜの予防接種の効果と副反応は?
おたふくかぜを予防する唯一の方法が、ワクチン接種です。
これを聞くと、
「そもそも、ワクチンって本当に効果があるの?」
と疑問に思う人もいるかもしれません。
でも安心してください。
ワクチンを1回接種している国では、発症者の数が88%も減少し、2回接種している国では、なんと99%も減少していると言われています。
ワクチン接種で起こる副反応
ワクチンを接種すると、まれに副反応が起こることがあります。
- 接種後10〜14日後に微熱が出る
- 耳やあごのあたりが少し腫れる
などですが、これらは自然に治ることがほとんどです。
「ワクチンで無菌性髄膜炎を発症する」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、その確率は40,000接種あたりに1人程度です。
おたふくかぜにかかった場合に比べて、その頻度ははるかに低く、症状も軽いです。
お子さんを合併症から守るためにも、ワクチン接種はとても大切なんです。
おたふくかぜの予防接種の回数や時期、費用は?
おたふくかぜの予防接種は、十分な予防効果を得るために計2回の接種が推奨されています。
【接種する時期】
- 1回目: 1歳の誕生日を過ぎたら、できるだけ早めに
- 2回目: 小学校入学前の1年間
です。
スケジュールを忘れてしまいそう…という方は、MR(麻しん風しん混合)ワクチンなど、他の定期予防接種と同時接種できるので、一緒に受けるようにすると安心です。
【気になる費用は?】
おたふくかぜの予防接種は、任意接種なので費用は自己負担です。
病院によって異なりますが、一般的に1回4,000〜6,000円です。
「え、そんなに高いの?」
と感じるかもしれません。でも実は、地域によっては、ワクチン接種費用を助成してくれる自治体もあります。
接種する前に、お住まいの市区町村の保健センターやホームページで確認してみてください。もしかしたら、タダで受けられるかもしれません。
「任意接種だから受けなくてもいいかな?」は危険!
おたふくかぜワクチンは、B型肝炎やロタウイルスのように、将来的に定期接種になる可能性があります。
ですが、現時点ではいつ定期接種になるかはっきりしていません。だからといって、「定期接種になるまで待とう」と考えるのは危険です。
保育園や幼稚園などの集団生活が始まる前に、おたふくかぜが流行するリスクは高まります。
もしおたふくかぜにかかってしまい、合併症で入院…となると、高額な医療費がかかるだけでなく、お子さんに辛い思いをさせてしまいます。
費用が自己負担だからとためらう気持ちもわかりますが、「お子さんの健康と将来への投資」だと考えて、早めに予防接種を受けることを強くおすすめします。
まとめ
おたふくかぜの予防接種について解説しました。
- おたふくかぜは、髄膜炎や難聴などの後遺症を残す可能性がある
- ワクチン接種は、おたふくかぜを予防する唯一の手段
- 十分な予防効果を得るために2回の接種が推奨されている
- 費用は自己負担だが、自治体の助成金がもらえる場合がある
- 任意接種でも、早めに受けるのがおすすめ
お子さんの健康を守るためにも、ぜひ今回の記事を参考に、予防接種を検討してみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

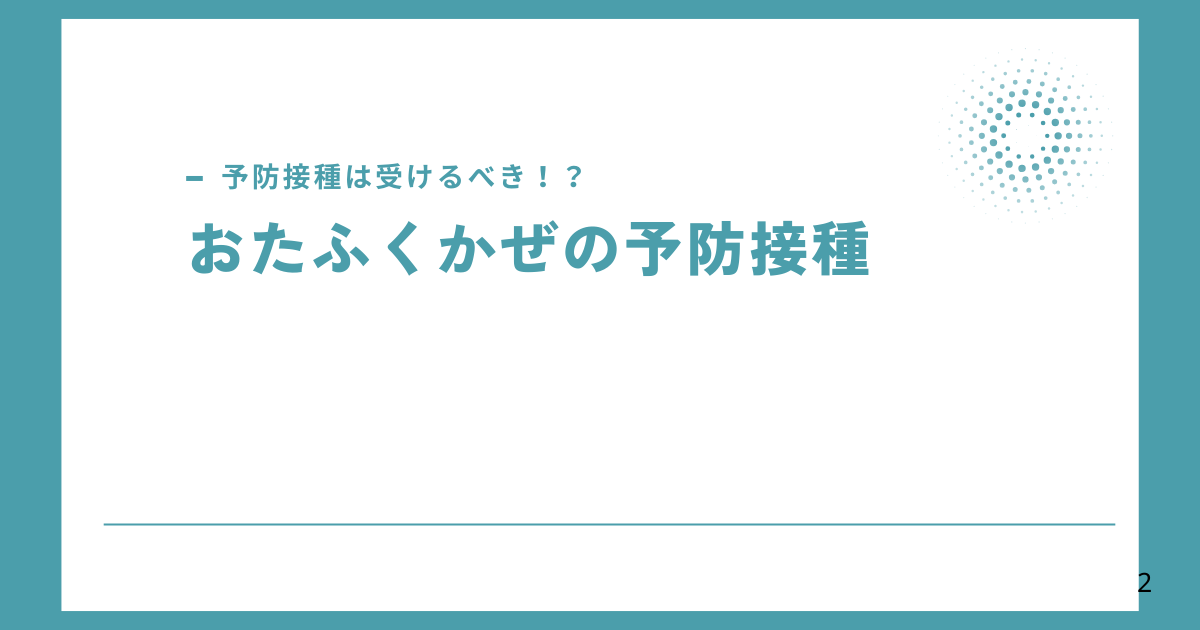

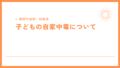
コメント