生後10ヶ月の赤ちゃんは、ハイハイやつかまり立ちなど、めざましい成長を見せてくれる時期ですね。行動範囲が広がる分、喜びも増えますが、同時に心配事も増えるパパやママも多いのではないでしょうか。
この記事では、生後10ヶ月の赤ちゃんの平均的な成長から、日々の具体的なお世話のポイント、安全対策、そしてこの時期にぴったりの遊び方まで、育児に役立つ情報を網羅的にご紹介します。
生後10ヶ月の赤ちゃんの身長・体重の目安は?
生後10ヶ月の赤ちゃんは、ふっくらとした新生児体型から、しっかりとした幼児体型へと変化していきます。運動量が増えるため、体重増加は緩やかになる子が多いのが特徴です。
厚生労働省の調査(平成22年)によると、生後10ヶ月の赤ちゃんの標準的な身長と体重は以下の通りです。
| 身長 | 体重 | |
| 男の子 | 68.4~77.4cm | 7.34~10.59kg |
| 女の子 | 66.5~75.6cm | 6.86~10.06kg |
上記の数値はあくまで目安であり、赤ちゃんの発達には個人差が大きいものです。大切なのは、成長曲線に沿って体重や身長が順調に増えているかどうかです。
もし、お子さんの成長に不安を感じる場合は、一人で悩まずに自治体の保健師さんや小児科医に相談してみましょう。
生後10ヶ月の赤ちゃんにこんな変化が!主な特徴まとめ
生後10ヶ月頃の赤ちゃんには、以下のような発達が見られることが多いです。もちろん個人差があるので、焦らずお子さん自身の成長を見守ってあげてください。
- 上の前歯が生えてくる:個人差はありますが、上の前歯が生え始める子もいます。
- 一人で座れるようになる:安定して一人で座れるようになり、遊びの幅が広がります。
- 5秒以上つかまり立ちができる:家具などにつかまって、数秒間立てるようになります。
- 大人が使っている物を真似る:大人の行動に興味を持ち、スプーンやリモコンなどを使いたがるようになります。
- 「ダメ」を理解し始める:「ダメ」と言われると、一旦手を止めたり、顔色をうかがったりするしぐさが見られます。
- 何でも口に持っていく:引き続き、手にしたものは何でも口に入れて確かめようとします。誤飲には最大限の注意が必要です。
- 指先が器用に:親指と人差し指を使って小さな物をつまめるようになる子もいます。
- おもちゃを引っ張ると抵抗する:お気に入りのおもちゃを取られそうになると、引っ張って抵抗する様子が見られることも。
社会性の発達とともに、パパやママへの愛着が強まり、後追いが激しくなる赤ちゃんもいます。「少しでも離れると泣き出す」「トイレにもついてくる」といった経験、ありませんか。これは赤ちゃんがパパやママを「安全基地」と認識し、絆が深まっている証拠でもあります。
そんな時は、会話やスキンシップの時間を増やして、赤ちゃんを安心させてあげましょう。「パパ・ママはここにいるよ」「すぐ戻るからね」と声をかけたり、抱っこしたりするだけでも、赤ちゃんは安心できます。
生後10ヶ月の赤ちゃんのお世話、ココがポイント!注意点も解説
行動範囲が広がる生後10ヶ月の赤ちゃんのお世話では、安全確保が最優先です。日々の習慣づけも大切にしていきましょう。
1. 歯磨き習慣を身につけよう
乳歯は、あごの発達や言葉の発音など、お子さんの成長にとって非常に大切な役割を担っています。虫歯予防のためにも、早めに歯磨きの習慣を身につけましょう。
まだうがいができない時期なので、赤ちゃん用歯ブラシで磨いた後は、ガーゼで優しく汚れを拭き取り、お茶や水を飲ませてあげましょう。
【赤ちゃん用歯磨きのオススメ】
赤ちゃん用歯ブラシ:ピジョン 仕上げ専用歯ブラシ など、月齢に合わせた安全な歯ブラシ
歯磨きナップ:和光堂 にこピカ歯みがきシート など、外出先でも手軽に使えるシートタイプ
2. コミュニケーションを増やそう!
「パパ」「ママ」などの単語を認識し始め、早い子では「マンマ」といった言葉らしい音を発することもある時期です。「はーい」「パパだよ」「ママだよ」と、赤ちゃんの呼びかけに積極的に応えてあげることで、コミュニケーションの楽しさを知り、心の成長を促すことができます。
何か動作をするときに「お風呂に入るよ」「これ、おいしいね」と具体的に話しかけることで、言葉の理解がより一層深まります。身振り手振りを加えると、赤ちゃんもより分かりやすく、楽しんでくれますよ。
3. 転倒・窒息・溺水に要注意!
つかまり立ちや伝い歩きを始めると、好奇心旺盛な赤ちゃんはすぐに手を伸ばし、危険な場所に近づいてしまいます。
- 転倒対策:階段にはベビーゲートを設置し、家具の角にはコーナーガードを取り付けるなど、徹底した対策が必要です。
- 溺水対策:お風呂のドアは必ず鍵をかけ、浴槽に残り湯を溜めないようにしましょう。
- 誤飲対策:タバコ、ライター、洗剤、電池、小さな部品など、命に関わるものは赤ちゃんの手の届かない場所に厳重に保管してください。床に落ちている小さなゴミやボタンなども、誤飲の危険性があります。
【オススメ商品】
- ベビーゲート:日本育児 おくだけとおせんぼ など、設置が簡単なタイプ
- コーナーガード・コンセントカバー:コンセントカバー など(こちらの記事で紹介しております)
- ベビーサークル:日本育児 洗えてたためるベビーサークル など、安全な遊び場を確保できるもの
言葉の発達は?生後10ヶ月の赤ちゃんとの「おしゃべり」を楽しもう
生後10ヶ月頃になると、赤ちゃんはパパやママが話す言葉の意味を少しずつ理解し始めます。
「パパ」「ママ」といった単語を記憶するようになり、早い子では「まんま(ごはん)」「だーだ(いないいないばあ)」といった、言葉らしい音を発することもあります。
赤ちゃんの言葉の発達を促すためには、積極的に話しかけることが何よりも大切です。
- 「あれ、なんだろうね?」
- 「おもしろいね!」
- 「ごはん、おいしいね」
など、日々の生活の中で感じたことや、赤ちゃんの行動に対して具体的に言葉にして伝えましょう。絵本の読み聞かせも、言葉のシャワーを浴びせる良い機会になります。
離乳食は「3回食」へ移行!生後10ヶ月の離乳食の進め方
生後10ヶ月は、離乳食が「後期」にあたり、順調に進んでいる赤ちゃんは1日3回食へと移行していきます。
離乳食の固さと目安量
- 固さ:歯茎でつぶせる熟したバナナくらいの固さが目安です。
- 目安量(1回あたり)
- 全粥:90g〜
- 軟飯:80g(子ども用茶碗に軽く1杯)
- 野菜・果物:30~40g
- たんぱく質(どれか1品):魚15g、肉15g、豆腐45g、卵(全卵)1/2個、乳製品80g
手づかみ食べをサポート
この時期は「自分で食べたい!」という欲求が芽生え、スプーンを使いたがったり、手づかみで食べたがったりする子が増えます。
一口サイズにカットした柔らかい果物や野菜、おやきなどを準備して、手づかみ食べをサポートしましょう。手づかみ食べは、赤ちゃんの指先の運動能力や、食べ物を目で見て認識する力を育みます。
離乳食の栄養バランスと鉄分補給
離乳食後期は、お腹の中でママからもらった鉄分が底をつき、貧血になりやすくなる時期でもあります。
ほうれん草や小松菜などの青菜類、レバー、赤身肉など、鉄分を多く含む食材を意識的に取り入れましょう。
離乳食を食べない時の対処法
無理強いは絶対にNGです。好き嫌いや食べムラが出てくる時期でもあるので、体調や気分によって食べないこともあります。
- 味のバリエーションを増やす:少量の調味料(だし、醤油、味噌など)を使って、風味を加えてみましょう。
- 調理法を変える:同じ食材でも、煮る、焼く、蒸すなど調理法を変えるだけで食感が変わり、食べてくれることもあります。
- 献立を見直す:1週間単位で栄養バランスがとれるように献立を調整しましょう。
アレルギー食材と「はちみつ」に注意!
生後10ヶ月の赤ちゃんは、まだ消化機能や免疫機能が未熟です。
- アレルギー食材:初めて与える食材は、少量から始め、アレルギー症状が出た場合に備えて、かかりつけ医を受診できる平日の午前中に与えましょう。
- はちみつ:乳児ボツリヌス症を発症する可能性があるため、1歳未満の赤ちゃんには絶対に与えないでください。
【離乳食オススメ商品】
- ベビー食器セット:ル・クルーゼのお皿セットや、落としても割れにくいシリコン製の食器
- ベビーエプロン:お食事エプロン 長袖 など、食べこぼしをしっかりキャッチできるもの
- 離乳食調理セット:コンビ ベビーレーベル 離乳食ナビゲート調理セットC など、初期から後期まで使えるセット
生後10ヶ月の授乳回数は?離乳食とのバランスを考えよう
生後10ヶ月頃になると、1日の栄養の多くを3回の離乳食からとるようになります。そのため、食後の授乳は次第に減っていくことが多いです。
- 母乳の場合:離乳食後に与え、その他は赤ちゃんの欲しがるだけ与えても問題ありません。
- ミルクの場合:1日2回程度が良いとされています。
無理に授乳量を減らすと、赤ちゃんが栄養不足になったり、慣れない変化に不安を感じたりすることもあります。赤ちゃんの様子をよく観察しながら、焦らずに進めていきましょう。
睡眠時間は?生後10ヶ月の生活リズムの整え方
生後10ヶ月の赤ちゃんの睡眠時間は、1日13時間程度が目安です。昼寝は1〜2回程度になり、夜にまとめて寝てくれるようになる赤ちゃんが増えてきます。
生活リズムを整えるコツ
日中の起きている時間は、なるべく活動的に過ごすことで、夜ぐっすり眠れるようになります。
- 日中にたっぷり遊ぶ:ハイハイや伝い歩きで部屋を自由に動き回らせたり、天気の良い日は公園など外へ出かけたりして、体をたくさん動かしましょう。
- 規則正しい生活:毎日同じ時間に起きる、寝る、食事をするなど、規則正しい生活リズムを心がけることが大切です。
- 寝る前のルーティン:お風呂に入って体を温め、絵本を読み聞かせたり、子守唄を歌ったりと、寝る前の落ち着いたルーティンを作ることで、赤ちゃんは安心して眠りに入りやすくなります。
- 夜泣き対策:テレビの音を消し、部屋を暗くして寝る環境を整えることも効果的です。
【睡眠の際のオススメ】
- ベビーモニター:パナソニック ベビーモニター KX-HC705-Wや我が家でも使っているCuboAiなど、夜中の赤ちゃんの様子を確認できるもの
- 絵本:だるまさんが や、じゃあじゃあびりびり など、繰り返し言葉や擬音が多い絵本
生後10ヶ月の赤ちゃんにおすすめの遊び方
この時期の赤ちゃんは、様々なことに興味津々です。好奇心を刺激し、五感を育む遊びを取り入れていきましょう。
1. 絵本の読み聞かせ
言葉の発達を促すためにも、絵本タイムはぜひ取り入れたい時間です。
- 選び方:分かりやすい色や形、繰り返し言葉や擬音がある絵本がおすすめです。動物や乗り物など、日常生活に登場するものが描かれている絵本も良いでしょう。
- 読み方:赤ちゃんのひざに座らせて、ママやパパの温もりを感じながら読んであげましょう。「これは何かな?」「きれいな赤色だね」など、赤ちゃんに語りかけながら読むことで、言葉の理解が深まります。
2. 体を使った遊び
ハイハイやつかまり立ちが安定するこの時期は、体を動かす遊びを積極的に取り入れましょう。
- 追いかけっこ:ハイハイで追いかけっこをしたり、つかまり立ちを促すようにおもちゃを少し離れた場所に置いたりするのも良いでしょう。
- ボール遊び:柔らかいボールを転がして、赤ちゃんに取ってきてもらう遊びもおすすめです。
3. 感覚を刺激する遊び
- 音の出るおもちゃ:振ると音が鳴るマラカスや、太鼓など、音が出るおもちゃは赤ちゃんの興味をひきます。
- ブロックや積み木:大きなブロックや積み木は、手で触ったり、積んだりすることで、空間認識能力を養います。
生後10ヶ月の赤ちゃんがかかりやすい病気と対処法
生後6ヶ月以前と比べて、ママからもらった免疫が弱まり、病気にかかりやすくなる時期です。しかし、免疫力をつけるためには病気にかかることも必要な過程なので、過度に心配しすぎる必要はありません。
生後10ヶ月頃の赤ちゃんがかかりやすい主な病気
- ノロウイルス胃腸炎
- ロタウイルス胃腸炎
- RSウイルス感染症
- アデノウイルス感染症
- ヘルパンギーナ
- 手足口病
- 突発性発疹症
大切なのは、赤ちゃんが病気にかかったときに、できるだけ早く対処してあげることです。
風邪っぽい症状や普段と違う様子が見られたら、迷わず小児科を受診しましょう。特に、高熱が続く、ぐったりしている、食欲がない、水分が取れないなどの場合は、すぐに受診してください。
まとめ
生後10ヶ月の赤ちゃんは、日々めざましい成長を見せてくれます。ハイハイで動き回ったり、言葉らしい音を発したりと、様々な方法でパパやママに訴えかけてくる時期です。
これまで以上に、赤ちゃんの感情表現が豊かになり、コミュニケーションが楽しくなるでしょう。積極的に話しかけたり、「これは〇〇だよ」と具体的に教えてあげたりと、赤ちゃんの反応にしっかり応えてあげることが大切です。
この時期は、パパやママとの関わりや、周りの環境からの刺激をどんどん吸収して成長していきます。赤ちゃんの成長を喜び、好奇心を大切にしながら、毎日のお世話を楽しみましょう。

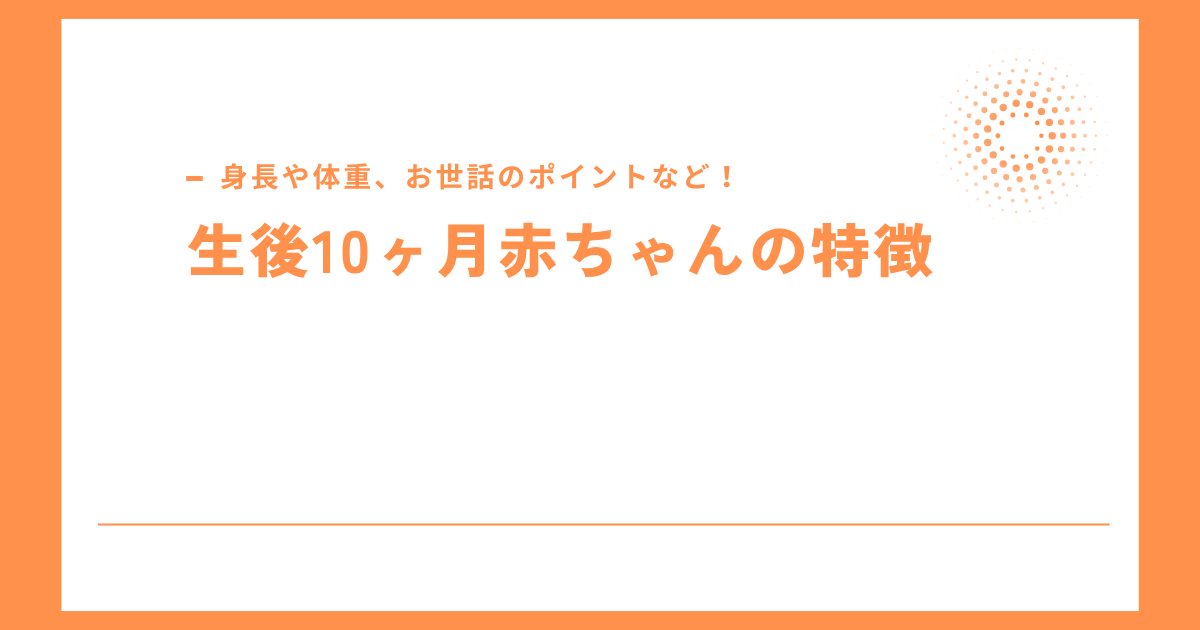
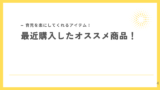
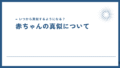
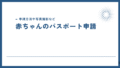
コメント